「子どもは褒めて育てよ」とよく言われます。
テレビや教育関係の雑誌、育児本でもしょっちゅう「褒める」ことの大事さが言われたり、書かれたりしています。
が・・・実際私たち、子どもの心に響く褒め方、しているでしょうか?
「褒めたってぜんぜん効果ないわー」なんて思ってしまってません?

(画像はみにぐり。手に持っているコントローラー含め、ゲームグッズをお片付けしないのが悩みです)
「自己満足褒め」に注意
先日図書館で借りた本を読んで気づかされました。この本です。
叱りゼロで「自分からやる子」に育てる本
自閉症や発達障害の子どもの支援をしている臨床心理士の方が書いた本です。
この本のケーススタディのひとつに、「リビングで散らかした後、片づけない」というのがありました。
おお!我が家でも同じ悩みがあるぞ。
どうやったら叱らずに片づけを身につけさせるか、書かれてました。
「必ずできることをやらせてまず褒めてください」
(1)「お片付けしようね」と声掛けしながらまずは親がある程度片づける。
(2)おもちゃが最後の数個程度・・・最初は4つぐらいから?になったら、子どもに片付けさせる。
(3)できたら大げさでもいいので思いっきりほめる。
(4)回を重ねるにつれ、だんだん子どもが片付ける比重を多くする。最終的には一人で片づけられるように。
で。。。この時のほめ方がポイントなのだそうです。
子どもがうれしそうにしているか
これをしっかり確認する。ここが重要。
(引用)
お母さんが褒めたかどうかが大切なのではありません。褒められた子どもが満足しているかどうか。うれしそうにして、また褒められるのを期待しているかどうかが大切なのです。
「褒めてあげた~」って親が思っているだけではダメだということ。
さらに重要なのは、「ほとんどお母さんが片付けているのに、子ども自身が片付けた気分になれる」こと。
これで子どもは「片付けたら、お母さんに褒めてもらえた」と思うようになるということ。パブロフの犬のような感じ?
我が家でもやってみました
特に散らかしっぱなしの放置状態をつくるのはうちの次男みにぐり。
「この部屋、片づけないといけないね」と言いながら、一緒にお片付け。
本人は一応、「やらなきゃいけない」意識はあるようで、片づけるおもちゃを手に取っていました。
それを片付け箱をもってきて入れさせる。
そんなこんなで片づけ完了。
やったーーー。かたづいたーーーー。みにぐりーーーえらいねーーーちゃんと自分で片づけたねーーーー。ホントえらいえらい♪
超がつく大げさっぷりで褒めまくりました。するとみにぐりは少し笑顔になり、
「(ごほうびに)抱っこして♪」と言いました。
迷わず抱っこしてあげました。
奥田流+ご褒美抱っこつき「片づけしつけ作戦」はまだまだ進行中ですが、とりあえず褒め褒めの効果はあったようです。
いいことをしたタイミングをすばやくとらえてほめるのが大事
奥田氏はほかに、
叱らず褒めていいことをどんどんさせるためには、普段から子どもの様子をしっかり観察して、いいことをしたタイミングをとらえてほめることが大事と言っています。
そして「その時が来るまで辛抱強く待つ」ことが大事と。
してほしいことをしなかったからといってムチを与えるのではなく、 「アメとアメなし」で対応せよ、とありました。
この場合の「アメ」は「褒めること」。うちの場合は「抱っこ」になりましたが。
これを粘り強く繰り返すことで、親が子どもに習慣づけさせたいと思うことをさせるのがしつけだと。
ただ、「子ども自身が『しなければならないこと』がわかってなかった」ということもあるので、まずは教え、やるのを待ち、できたら褒める、が有効なのかなとも思います。
そのほか「自分からやる子」に育てるために大事なこと
今回の記事は、「叱りゼロで「自分からやる子」に育てる本」の第一章部分の内容。
他にも「やめさせたい癖をやせさせるには」「我慢を育てるには」「自分からやる子に育てるには」について書かれています。
そこらの心理系の人が言いがちな生ぬるいことは書かれていませんので、覚悟のうえで(?)お勧めです。
私もけっこう「痛い」と思うことが書かれてました^^;



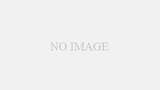
コメント